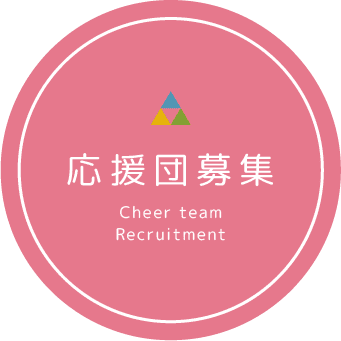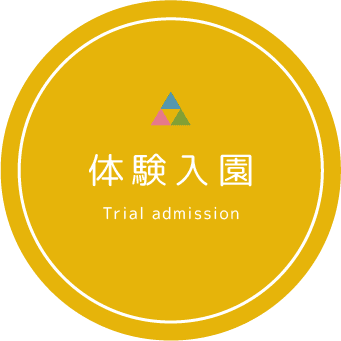記事一覧
もりあそびより
オアシスのようなコミュニティ
- 園の日常

先日、子どもたちのお迎えの際、ある保護者の方が少し顔色が悪く、
体調がすぐれないご様子でした。
翌日のお迎えの際、連絡をして「子どもたちを連れて帰りましょうか?」と
お声がけしたところ、「もう随分良くなりましたし、
今日は家族がお迎えに行ってくれるので大丈夫です」とのことでした。
それまでの送迎の際に十分お手伝いできなかったことが心に残り、
「また何か困ったことがあったら、いつでも知らせてくださいね」と
メールを送りました。すると、返ってきたのは、
「さゆりさん、ありがとうございます!困った時は相談してみます。
もし、さゆりさんも困った事があったら声掛けて下さいね。」という言葉でした。
その一言に、思わず膝から崩れ落ちて溶けてしまいそうな、
そんな感覚に襲われました。
長年、子育て支援の活動を続けてきて、
もちろん多くの方に助けていただく場面もたくさんあったのですが、
実際にこんな風に当事者の方から逆に「お互い様ですよ。あなたも困ったら助けてって言ってくださいね。」と声をかけられることは、これまでありませんでした。
人には、「困ったら助けてって言っていいんだよ」と伝えながら、実際には自分が「助けて」と言う勇気を持てていないことを、その方の言葉に見透かされたような気がしました。
ふと、子どもが小さい頃、友人たちと助け合いながら子育てをしていたことを
思い出しました。誰かが体調を崩したら夕飯を作ったり、
兄弟児を預かったり、幼稚園の送迎をみんなで協力してこなしたりしていました。
私自身、次男を妊娠の際に切迫早産で3か月ほど寝込んでいた時期も、
夕飯が毎晩どこからともなく届き、
昼間は長男は誰かのお家で遊ばせてもらうなど、
多くの支えを受けて過ごすことができました。
でも、子どもが大きくなると、そういった助け合いも自然と減っていくものですよね。昨年の11月、12月に体調を崩し、天井を見上げながら
「もうあの頃のような支え合いはないんだな」と感じていた矢先、
今回のような言葉をいただけたことが、本当に嬉しかったです。
今は共働きの保護者が増え、気軽に立ち話をしながら悩みを共有したり、
誰かの危機を察して助け合ったりする「井戸端会議」のような機会も減り、
大変な時代になったと感じます。
こんな時代だからこそ、相手が誰であれ困った時に「助けますよ」と
自然に手を差し伸べることが出来る、そんな温かいオアシスのようなコミュニティを
「もりのこえん」で育んでいけるといいなあと思っています。
(このエピソードは保護者の方の了解を得て、掲載しています)