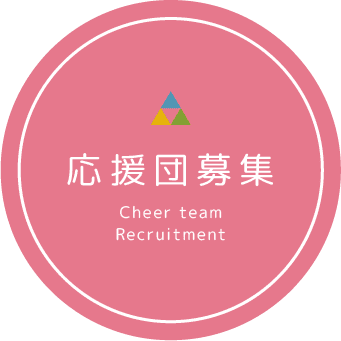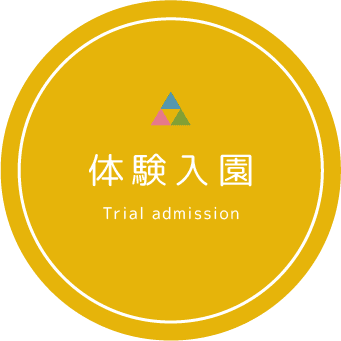記事一覧
もりあそびより
安心感の上に
- 園の日常
- 森のイバーショ

fb安居 長敏さんより
今日、本校の学校説明会で、受験を考えておられる親御さんのご質問にお答えしながら、「子育て」や「教育」について率直にお話しする時間がありました。漠然とした不安を抱えながらも、だからこそ我が子にとって最適なものを一生懸命に考えていらっしゃる――その思いに強く触れるひとときでした。
戦後の日本では、基幹産業が農業から工業に移り変わる中で、工場の製造モデルがそのまま学校教育に持ち込まれました。材料を揃え、ベルトコンベアに乗せて加工すれば、決まった納期に規格通りの製品ができあがる――そんな「工程管理」を教育に適用し、人間に「機械になれ」と求めたのです。
規律訓練、個性の剥奪、集団行動。ペーパーテストや授業態度で数値化され、模擬テストの偏差値でランク付けされ、新卒一括採用につながる。こうした仕組みは、高度経済成長期の豊かさと相まって、「教育とはそういうものだ」という思い込みを社会全体に浸透させました。努力不足を責められても疑わなかった時代。「それで何とかなった」経験を持つ世代が、いまなお社会の上層を占めているのです。
私自身も、その中で育ちました。
あと半月で66歳になる私は、1960年代後半、兼業農家が増え始めた田舎で小学校に通っていました。家庭環境に大きな差はなく、流れ作業のように「画一的」な教育を受けることに、当時は大きな疑問を抱かなかったのです。むしろそれ以外の選択肢を想像する情報もなく、「流れに乗ることが明日のため」だと信じていました。大人たちもまた、高度経済成長の恩恵を生活の向上として実感できる、幸せな時代を生きていました。
だから、学校が「何かを試され、順番をつけられ、緊張を強いられる場」であることも当たり前でしたし、それを「成長のための試練」だと思っていました。それでも壊れずにいられたのは、帰れば成績も能力も問われない「家族と過ごす場所」があったからです。結果や能力を常に試される学校や企業のような「学校化」された場に身を置くからこそ、家に戻って肩の力を抜き、安心できる時間がある。その存在があったからこそ、生きてこられたのだと思います。
しかし今の時代、状況は大きく変わりました。かつては「学校や会社で試されても、家では安心できる」という補い合う構造がありましたが、いまや家庭や地域そのものが余裕を失い、子どもにとっても大人にとっても「ホッとできる場所」が揺らいでいます。社会全体が不安定化し、私たちを取り巻く世界は「対策不能な課題」にあふれているのです。前提条件すら曖昧で、正解がない。
だからこそ教育の役割は、「未知に向き合う力」を育むことにあるはずです。正解をなぞらせるのではなく、情報を集め、かみ砕いて判断し、行動していく経験を積む。その過程で、自分の言葉で語り、失敗を受け止めながら進んでいけるマインドとスキルを学ぶことが大切です。
また、こんなふうに考えを重ねる中で、改めて思い至ったことがあります。
それは、学校が「家のような安心感」をすべて提供しようとすることには無理がある、ということです。制度的にも、教職員の働き方の面から見ても、それを丸ごと担うことはできません。むしろ大切なのは、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を補い合いながら、安心を分かち合う仕組みをつくっていくことだと思います。
学校は「安心のすべて」を独占する場ではなく、子どもが挑戦できる環境を整え、その挑戦を安心して行えるよう「信頼できる空気」をつくることに集中するべきでしょう。挑戦が行きすぎたときには家庭が受け止め、家庭で抱えきれないものは地域が支える。学校もまた、そのつなぎ役として機能する。そうした三層のネットワークが、子どもたちの安心を下支えするはずです。
同時に、学校に「家の代わり」を期待しすぎる社会的な幻想を解きほぐすことも欠かせません。学校はすべてを引き受ける場所ではなく、子どもが挑戦し、その過程で伴走してもらえる場所である――そうした認識を共有していくことで、教育の持続可能性も高まっていきます。
そして何より重要なのは、「安心」と「挑戦」をセットでデザインすることです。安心だけでは成長はなく、挑戦だけでは心が持ちません。その両者を行き来できるように学校生活や学びの仕組みをつくる。たとえば、本校のハウス活動や日常的に相談できる関係性は「安心」、探究や発表の場は「挑戦」。そうしたバランスの中でこそ、子どもたちは力を伸ばしていける一つの形だと考えています。
こうした実践は、本校に限った取り組みにとどまるものではありません。多くの学校が、子どもたちに「未知に挑む力」と同時に「安心して挑戦できる場」を育む存在となってほしいと、心から願っています。